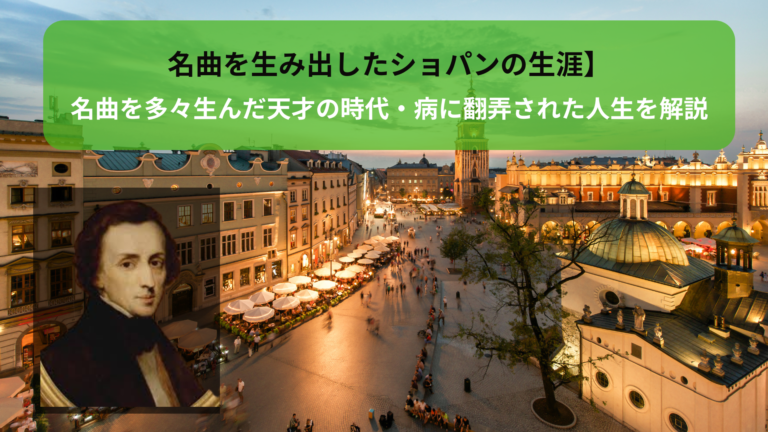ピアノ曲の作曲にこだわり、多数のピアノ曲の傑作を生み出したフレデリック・フランソワ・ショパンは、「ピアノの詩人」とも呼ばれています。
数々の大作曲家の中でも、”天才の中の天才”と呼ばれるショパンですが、その人生は時代に翻弄され病に苦しんだ壮絶なものでした。
本記事では、ショパンの人生から知っておきたい名曲・代表作を紹介していきます。
フレデリック・フランソワ・ショパンの人生
フレデリック・フランソワ・ショパン(Fryderyk Franciszek Chopin)は、1810年3月1日に生まれ、ポーランド出身の作曲家ピアニストです。
主にピアノ曲の作曲で著名で、個人の感情表現や主観的な世界観を重視したことが特徴のロマン派音楽を代表する作曲家の一人です。
ショパンの叙情的で繊細なメロディ・和音が多く聴く人の感情を深く揺さぶる豊かな感情表現とリリカルな旋律美を確立した、繊細で詩的な作風と高い演奏技術で多くの人を魅了し続けています。
ショパン自身が高い演奏技力を持つピアニストということもあり、作品には高度なピアノ技法がふんだんに盛り込まれていますが、リストのような「派手さ」を追求するのではなく、あくまで音楽表現の一部として繊細に活かされている曲が特徴です。
ここからは、ショパンの人生を幼少期から青年期、そして晩年にかけて流れとともにご紹介します。
フレデリック・フランソワ・ショパンの幼少期(0歳〜16歳)
.png)
ショパン本名(フレデリック・フランソワ・ショパン)は、1810年にフランス人の父ミコワイとポーランド人の母ユスティナの基に生まれました。
ショパンの父ミコワイは、フランスの庶民の家に生まれましたが、当時では珍しい読み・書きができる少年で、その才能はフランスに赴任していたポーランドの役人の目に留まり、役人の帰国に伴いフランスからポーランドに移り住むことになります。
その後ミコワイは家庭教師先の貴族の娘ユスティナと結婚し、結婚の翌年に長女のルドヴィカ、長男フレデリック、次女イザベラ、三女エミリアと子宝に恵まれました。
2番目に生まれた唯一の男子がフレデリック・ショパンで、のちの音楽史に名前を残す人物となります。
母のユスティナはピアノと歌が得意ということもあり、ポーランド民謡を子守唄に歌ってもらい、父のミコワイはフルートやヴァイオリンの演奏が大好きで、日常的に音楽に触れる環境で育つこともあり、次第にピアノに興味を持つようになりました。
フレデリック・ショパンは、4歳から母や姉を見習いピアノを弾き始めるようになりました。
6歳では即興演奏でも才能を示すようになり、音楽教師のヴォイチェフ・ジヴヌィにピアノを習い始めるようになり、幼いながらもすでに優れた演奏技術を持っていました。
当時ヨーロッパの列強に支配されていた、ポーランド、ワルシャワの人々は自国の芸術・文化に大きな情熱を持ち、ショパンは8歳にしてワルシャワの貴族たちのサロンに呼ばれるようになりました。
※当時のサロンは、宮廷や貴族の夫人の邸宅でお互いの交流を深めるために開かれた社交の場です。
12歳になったショパンは、さらに音楽の理解を深め、父の友人であるワルシャワ高等音楽学校校長:ユゼフ・エルスネルから作曲を教わり、同じくワルシャワ口頭音楽学校でピアノを教えていたヴィルヘルム・ベルフェルからオルガンを教わるようになります。
この二人の先生たちも幼いショパンの類まれなる才能を最大限尊重する指導方法でした。
ショパン一家は、当時ワルシャワ大学やワルシャワ高等学校が所在していたカジミェシュ宮殿の一角に住んでいたこともあり、父ミコワイの教授仲間や学生が頻繁に行き来する環境で学問の基礎は父や学生から学ばせるという父の教育方針も関係し、ショパンが音楽に時間を費やせる環境で育ちました。
また、ショパンは友人にも恵まれ、ショパンの親友であるティトゥス・ヴォイオチェホフスキはショパンにとって特別な存在で控えめな存在のショパンに対して、リーダーシップのあるしっかり者のティトゥスは2歳歳上で共にジブニィに音楽を学びました。
16歳頃のショパンはワルシャワ音楽学校の中でも、『段違いの才能』とされ、マズルカやポロネーズ、ワルツ、ロンドなど様々なピアノ曲を次々に作曲していきました。
フレデリック・フランソワ・ショパン:音楽家の道へ(16〜21歳)
.png)
当時から、ショパンの実力はポーランド国内に収まるものではなく、明らかに突出した実力で、1829年の19歳の時にワルシャワ高等音楽学校を主席で卒業し、音楽学校の仲間たちと「音楽の都」ウィーンへ卒業旅行に行きます。
そこで、かつてのオルガンの師であるヴュルフェルに再会し、卒業旅行中にヴュルフェルと共にケルントナートーア劇場で演奏会を開くことになりました。
2度行った演奏会はどちらも大成功で終わり、その興奮を家族への手紙にこう記しています。
オーケストラのトゥッティ(全合奏)が聞こえないほどでした。
こういった種類の音楽を聴いたことのない聴衆には衝撃的な感動だったようです。
その演奏会については、ワルシャワでも大々的に報じられ、ショパンが卒業旅行を終えワルシャワに帰国した時にはウィーンでの演奏会の成功で有名になっていました。
ショパンは帰国後すぐに作曲に取り組み、ピアノ協奏曲第2番を初めて作曲しました。
ショパン:協奏曲第2番
ショパンの協奏曲第2番は、ショパンがまだワルシャワで学んでいた1829年頃に作曲された曲で、当時20歳弱という若さで、初期の作品ながらも詩的で繊細なピアノ技法を感じられる一曲です。
伝統的なソナタ形式に準しており、オーケストラ形式の序奏につづきピアノが主題を奏でる一曲で、調性がヘ短調ということもあり、憂いを帯びたドラマスティックな雰囲気で進行しつつもショパン独特のリリカルな歌心が随所に現れています。
第一楽章では伝統的な協奏曲形式を踏襲し、Maestroという指示のように、やや重厚でドラマティックな導入でショパンの協奏曲では珍しく、最初の主題からある程度の悲愴感や情熱を感じられる旋律が登場している曲です。
彼女を思いながら協奏曲のアダージョ(第2楽章ラルゲット)を書いた。今朝はさらに小さなワルツも書いてみた
ショパンはワルシャワ音楽学校在学中から思いを寄せ、卒業後も想いを寄せ続けていました。
コンスタンツヤに宛てた手紙で記されたワルツというのは、ワルツ第13番変ニ長調のことで、甘美なメロディと溌剌とした響きを持つ青春の傑作の一つです。
ショパン:ワルツ第13番
ワルツ第13番は、広く知られている子犬のワルツとして知られるOp.64-1とは別作品で、冒頭から明るくエレガントな主題が始まり変ニ長調特有の柔らかな響きを生かした一曲です。
”長調のワルツらしい”、ウキウキとしたリズム感と穏やかな雰囲気が特徴で、「子犬のワルツ」と比べるとやや落ち着いた趣があるとされています。
シンプルな構成ながらも、旋律にはショパンらしい装飾や細かなリズム変化が施されており、一瞬の中に様々な曲の雰囲気が込められ、中間部の調やキャラクターの変化によって、音楽の彩りと起伏が生まれていることも特徴です。
その後、ショパンは音楽家として更なる成長のため、コンスタンツヤのいるワルシャワを離れる決意をし、卒業旅行で訪れた「音楽の都」ウィーンへ親友のティトゥスと共に移り住むこととします。
しかし、前回のウィーン旅行とは異なり、移り住んだウィーンでの生活は思うようには上手くいかないものでした。
さらに、12月には祖国ワルシャワで11月蜂起が起こり、親友ティトゥスは祖国で戦うことを決意し祖国に戻りましたが、ショパンは体が丈夫ではなかったこともあり父に説得されウィーンに一人残る決意をしました。
・ティトゥスの帰国に伴う強い孤独感
・11月法規に伴い、ショパンに対してもウィーンで冷ややかな視線
ウィーンでの新生活に期待を持っていたショパンは上手くいかない生活がさらに絶望になりました。
そして、1831年7月ショパンが21歳の頃、ショパンはパリを経由してロンドンに向かうことを決意しました。
道中でショパンは、ロシア軍によってポーランドの蜂起が失敗したことを知り、祖国の家族・友人知人の安否不明でありながらも帰国することができない状況で、作曲された曲がエチュード第12番『革命』とされています。
エチュード第12番『革命』
激しく打ちつけるようなリズムとうねり、叫びのような曲の雰囲気は当時のショパンの胸中を表すかのようなもの。
冒頭から左手が連続して疾走するような16分音符で奏でられ、右手は力強い主題を高らかに響かせる全体的に熱情的でドラマティックな雰囲気で強い哀愁と緊張感を孕んでいる曲です。
多くの転調を重ねたスピード感のある曲で、旋律だけ聴くと悲壮感や悲しみが漂いますが、同時に燃え上がるような熱情や、ショパンの内面にある「祖国を奪われた無念の思い」や「故郷への愛着」といった抗いの感情も感じられる一曲です。
ショパンはパリに到着:パリでの活躍(21歳〜27歳)
当時のパリには、ワルシャワを離れたポーランド人も多数生活しており、ショパンの知り合いもいたため祖国の仲間のおかげで徐々に穏やかな気持ちになり、パリでの生活はすぐに溶け込むことができました。
ショパンがパリでの生活にすぐに溶け込むことができたのは、パリ音楽会の重鎮であるフェルディナンド・パエルなどに対しての紹介状を持っていたことも関係しています。
そこで、パエルは弟子であるヴィルトゥオーソ・フランツリストを紹介し、
.png)
内向的で繊細なショパンとに対して、大胆で華やかなリストは対照的でしたが、芸術性を理解しすぐに打ち解けることができ、リストはショパンに対してこのように称賛しています。
まるで生まれながらの王子のようだ
また、リストだけでなく天才音楽家のフェリックス・メンデルスゾーンやチェリストのオーギュスト・フランコムのような当時のパリの音楽界の中心的人物たちに歓迎され、音楽家仲間と親交を深めました。
ショパン:エチュード第3番『別れの曲』
この曲を含む「12のエチュード集」はショパンがリストに献呈したもので、同じ曲集に収録されている12曲のうち最後に作られた作品です。
ショパンのエチュード(練習曲)という形でありながらも、演奏技巧だけでなく詩的表現・叙情性・色彩感に富んだ作品で、特に「メロディが美しい」として有名で多くのピアニストが愛奏する作品です。
この曲の最大の魅力は、冒頭から登場する美しく伸びやかな主題メロディにあり、寂寥感や郷愁を伴った雰囲気があります。
穏やかなで叙情的な冒頭に対して、中間部ではより情熱的な劇的な展開がされ、強弱の幅の広がりと右手・左手の動きが増し曲全体に大きなコントラクストが生じている作品です。
ショパンが23歳ごろのパリでは、コレラ自粛による人前での演奏機会が減少するなどの影響、パリ音楽界のレベルの高さを実感し、自分が音楽界で生き残っていくための策を慎重に模索し続けていました。
そこで、パリのサロンで出会った貴族の女性や子供に対してレッスンをはじめ、生計を立てていたとされています。
ショパン:ワルツ第1番『華麗なる大円舞曲』
華麗なる大円舞曲は、初めて世間に発表したワルツ作品で、教え子ローラ・オースファールに献呈した曲です。
ショパンのワルツの中で最も華麗で軽妙・爽快な作品で、ウィーン風の踊りのためのワルツというよりも、サロン向けに洗練された”演奏会用ワルツ”として印象が強い曲で、華やかで演奏会映えする要素が多い曲です。
ただし、単に派手な曲というのではなくショパンらしい繊細な詩情や優美な印象があり、当時流行していたウィーンの舞踏会のワルツに比べると踊ることよりも”聴かせること”を意図した”サロン的”な性質が際立つ一曲です。
1832年、22歳になる前にショパンは念願のパリでのデビューコンサートを行います。
ショパン:即興曲第4番『幻想即興曲』
幻想即興曲は4つの部分で構成され4/4拍子のリズムが特徴的な一曲です。
右手は16分音符のシクタプルを、左手は8分音符のトリプレットを使用していることが、幻想即興曲の独特な雰囲気を醸し出しています。
冒頭部から激しく波打つようなパッセージで右手が繰り返され、左手がそれとリズム的に複雑な絡み合いを見せ、曲名の通りまるで即興曲のような自由奔放かつ疾走感を受ける一曲です。
その噂が広まり、多くの貴婦人がショパンに教えを請うも、ショパンは音楽的才能がないと教えないことを決めていたため、多くの人に教えることはしませんでしたが、少数精鋭のショパンの教え子たち、関わった貴族たちからは絶大な信頼を獲得していました。
そして、1835年ショパンが25歳ごろに故郷を出て5年ぶりに両親に再会することができました。
ロシアの監視が薄い、現在のチェコ:カルロヴィ・ヴァリで落ち合うことになり、3週間ほどの滞在はショパンにとって離れがたい時間でもあり、200km先ポーランド国境付近まで両親を見送っていたともされています。
その道中、ドイツのドレスデンにて、昔の寄宿生のフェリックス・ヴォジンスキを訪ねます。
この時、マリアとの別れを惜しんだショパンが彼女に捧げた曲が、ワルツ第9番別れです。
ショパン:ワルツ第9番「別れ」
優雅な旋律の中に愁と陰りを感じさせ、ノスタルジックなメロディーを持つ一曲です。
1835年の9月にドリスデンで作曲されたとされ、マリア自身がこの曲を『別れのワルツ』と名付けて愛したといわれています。
冒頭から右手の旋律が静かに歌い始め、独特な詩情を醸し出し、ショパン特有の「歌うようなメロディ」と絶妙なルパート(テンポを揺らすような表現)が求められる繊細で抒情的な旋律を感じられます。
その後、無事体調が回復し、1836年の夏にマリアにプロポーズをしに行きます。
再会までの間二人は手紙でやり取りを続け、愛を深めており、ショパンのプロポーズに対してマリアは喜んで受け入れました。
ショパンの健康状態を把握するため、生活習慣や就寝時間に関する命令をマリアの母が行うほど徹底していたのですが、ショパンは1837年にインフルエンザになってしまい、そのことをマリアの母が知ることとなり、ショパンとマリアの婚約は解消されてしまいました。
そのころに書かれた曲がエチュード23番『木枯らし』です。
ショパン:エチュード23番『木枯らし』
木枯らしは、行進曲風のリズムを左手で奏でながら右手は半音階的パッセージを演奏する曲で、嵐のように渦巻く急速な右手のパッセージが寒風吹き荒ぶ冬の風景を連想させることから「木枯らし」と呼ばれるようになったとされています。
短いゆったりとしたイントロから始まり、すぐに激しく吹き荒れる”木枯らし”のような急速パッセージへ突入する曲はイントロ部分の暗く、どこか不穏な雰囲気を漂わせ、やがて急転直下で激しい疾走感を伴う本編へと移り変わっていきます。
左手がメインとなって旋律を担う部分が多く、右手の華やかな動きに隠れがちですが、左手こそ曲の”歌”や骨格が存在し、ショパンのエチュードの中でも、右手の技巧と左手のメロディがこれほど対照的に配置された曲は珍しい一曲です。
また、フォン・ビューローはショパンの「木枯らし」に対してこのように語っています。
全くオーケストラ的ではなく完璧な意味でのピアノ音楽」
ショパンの新たな生活(27歳〜34歳)
マリアとの婚約が解消され、失意のどん底にいたショパンは休暇をとり気晴らしにロンドンなどへ旅行に行き、少しずつ回復してきたものの心の傷は完全には癒えませんでした。
そうしたショパンに熱心に口説いていた女性が存在し、人気作曲家デュドヴァン男爵夫人のジョルジェ・サンドがいました。
ショパンとサンドが出会ったのは、ショパンとマリアがまだ婚約していたプロポーズの翌月ごろのことで、リストの紹介で初めてショパンの演奏を聴き、非常に感動し、それ以降ショパンに心を奪われていました。
当時のサンドは、当時の女性では珍しく経済的・精神的に自立した女性で、古い慣習にとらわれず、愛する男性に積極的にアプローチする情熱的な女性とされていました。
サンドはショパンに対して熱心なアプローチをしていましたが、ショパンはサンドに対して女性的な魅力を感じておらず、マリアの存在もあり断り続けていました。
しかし、マリアとの婚約解消で心身疲弊していたショパンをサンドは優しく包み込んでくれ、強く逞しいだけでなく母のように優しいサンドにショパンは次第に惹かれていくようになります。
その後ショパンとサンドは親しくなり、サンドの子供も引き連れて4人でマヨルカ島に行きます。
マヨルカ島では治安が悪く、雨季の体調不良、ピアノが届かず、ショパンの体調は悪化してしまいます。
ショパン:前奏曲第15番『雨だれ』
抒情的な旋律の美しい作品で、雨だれの名のもとになった変イ音が冒頭から最後までほとんど途切れることなく反復され、まるで雨だれのように聞こえることが由来です。
ゆったりとした流れの中で響き連続音は、落ち着きと同時に心の奥底に小さな不安や寂しさも感じさせるという独特の表情を作り出し、調性が一転したパートからは、激しく重々しいムードへと移り変わります。
その後、再び静けさと安堵感が訪れる曲で、ショパンがサンドと滞在したマヨルカ島でのエピソードが絡み「雨音を聴きながら作曲したのでは?」ともされている一曲です。
その後ショパンが29歳の頃、フランス ノアンにあるサンドの別荘に移り住むことになり、サンドの使用人たちのおかげもあり、とても心地よく生活することができていました。
しかし、ショパンは田舎ノアンでの生活に退屈し、再びパリに一人で戻ることに決意しました。
パリに戻ったショパンは大歓迎を受け、1841年ショパンが31歳の時、パリで大演奏会を行いました。
その頃から、ショパンとサンドは夏はノアン、冬はパリという生活をスタートさせ。、
ショパン:ポロネーズ第6番『英雄』
ショパンの円熟期の名作のひとつで、技巧的で壮大かつ堅固な後世の作品です
リズムや和製においてさまざまな工夫が施されており、楽想の変化に富む傑作
華やかで力強い主題と逞しいリズムが勢いよく演奏され、演奏者には非常に高度な技術が求められます。
冒頭から鳴り響く和音や重厚な伴奏リズムが、非常に力強く雄大な印象を与え、全体を通して華やかさ・威厳が融合し、英雄的と評される所以の堂々たる雰囲気を感じられます。
ショパンの多くのポロネーズに共通するように、右手・左手ともにピアノの広い音域を駆使し、音の厚みや迫力を表現している
ショパンの別れと晩年(34歳〜39歳)
しかし、次第にショパンとサンドの関係が歪みはじめ、1847年ショパンが37歳の頃時、別れました。
この頃に作られた曲がワルツ第7番嬰ハ短調で、嬰ハ短調という調性が示すように全体的に哀愁や内面的な叙情性が感じられるワルツです。
ショパン:ワルツ第7番嬰ハ短調
どこかもの悲しさを漂わせつつも、優美さを併せ持つメロディが印象的で、曲の中間部ではより穏やかで明るい雰囲気を帯びる展開になり、『暗→明』のコントラストが作品を際立たせている一曲です。
3拍子系の舞曲で、強-弱-中もしくは弱-強-中のような独特のリズム感が出ることが特徴で、ポーランドの農村や農民の活気、素朴さを感じさせるような軽快でありながら、どこか土着的な情緒を持ったマズルカ風のニュアンスのあるリズム感も特徴です。
ワルツという性格上、3拍子の拍感がベースにありつつも、ショパン特有のルパート(絶妙なテンポの伸縮)や、左手の伴奏形との組み合わせによって、単に軽快な舞曲とは異なる繊細な雰囲気を感じられます。
サンドと別れた翌年の1848年に、ショパンは弟子の誘いもありイギリスのロンドンに移ります。
ショパンはロンドンで演奏旅行やレッスンなどを始めましたが、パリとの生活の勝手の違いに次第にストレスを感じるようになり、体調不良になりました。
そして、同年の冬にパリに戻ることにしたものの、ショパンの体調は優れず、診察代を稼ぐためにもピアノのレッスンは続けなければならず、体調は悪化し続けたとされています。
その後、ショパンの体調はピアノの前に座ることも作曲のためのペンを握ることもできないほど体調が悪化し、
そして、1849年10月ショパンは39歳という若さで亡くなりました。
まとめ:【ショパンの生涯】今でも広く知られる名曲
如何でしたでしょうか?
繊細なメロディで聴く人をワクワクさせるような曲を生み出したショパンですが、こうした名曲が生まれた背景には祖国ポーランドの情勢や愛する人との出会いや別れ、病気に悩まされていたことが影響しています。
繊細で、情熱や悲壮感おも感じることができる曲のショパンの名曲は楽しい時、悲しい時、頑張りたい時、落ち着きたい時など多くの場面で聴きたいです。