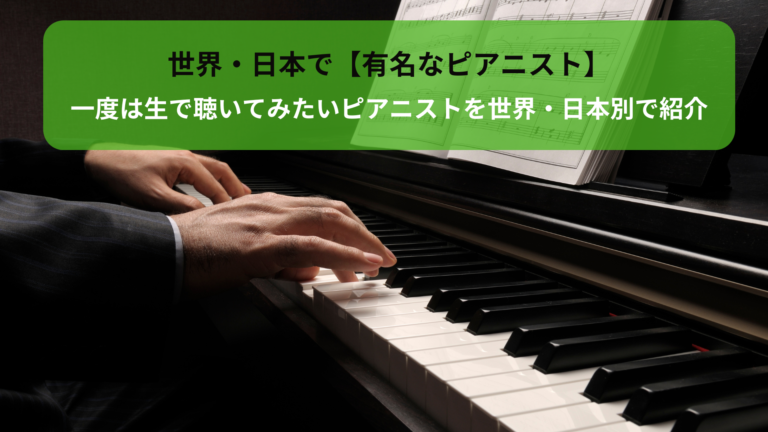テレビ、YouTubeなど身近にクラシック音楽を聴ける世の中になりました。
特にピアノ曲は癒される音楽で人気は不動のものです。しかし、良い曲だなと思ってyoutubeで検索してみると、たくさんのピアニストが出てくるのではないでしょうか?
そんなあなたに、実力はもちろん、人間性も紹介して「へーこんな面白い人がいるんだ!」と違った切り口から興味を持っていただきたいと思います!
一生に一度は生で聴きたい!世界的に有名なピアニスト8名
”たった、一音でも空気が変わる瞬間”を体験したことがありますか?
ピアノの生演奏がもたらす感動は、音源や映像だけでは味わいきれないような特別なもの
世界には、”その場にいるだけで息をのむ演奏”をするピアニストが存在します。
そのピアニスト達のびっくりエピソードも含めた人間としての魅力、音楽の魅力に触れます!
今回は、一度は生で聴きたい!と切望される世界的ピアニストの魅力と、その理由をご紹介していきます。
ダン・タイ・ソン
戦争中は紙の上にピアノの鍵盤の絵を描いて指を動かしていた、ショパンを愛するピアニスト!
ベトナム出身のピアニスト、ダン・タイ・ソン。
1980年にアジア人で初めてショパン国際ピアノコンクールで優勝し、ポロネーズ賞、マズルカ賞、 コンチェルト賞も合わせて受賞するという世界に新しい風を吹かせた人物です。
現在はカナダを拠点に世界中でコンサートを行い、多くのオーケストラと共演しています。また、教育活動も行い、多くの若手ピアニストを指導しています。
そんな輝かしい経歴のダン・タイ・ソン。
皆様はベトナムというとどんなイメージがありますか?
「料理(フォーやバインミーなど)が美味しい。」
「道路はバイクがいっぱい走っている。」
「たくさんの民族がいるから多種多様な文化が入り混じっている。」
など、ベトナムは日本と食文化も似ており、飛行機で比較的訪れやすいことから、観光地としてのイメージが多いのではないでしょうか。
知れば知るほどベトナムという国への好奇心が湧いてくると思います。
しかし「発展途上国」というイメージは無視できないです。
発展途上国というと、一概には言えませんが軽犯罪が多く治安が不安定ということも事実です。
実際ダン・タイ・ソンの子ども時代(17歳頃まで)はベトナム戦争があった時代でした。
彼は5歳の時にピアノの練習を始めたのですが、戦争の渦中なのでピアノの練習も思うままにできなかったことでしょう。実際に防空壕で生活していましたし、手元にピアノがない状況でした。
そんな中でも、少年ダン・タイ・ソンのピアノへの熱意は消えることはありませんでした。本物のピアノが使えなかった時は、紙に鍵盤を描いて練習したというエピソードは今でもダン・タイ・ソンという人物を語る上で外せないエピソードです。
またピアノは水牛の背に乗せて運ばれ、湿気でボロボロになりました。毎朝、鼠を追い払った後に練習を行い、晴れた日にはピアノを地上に引きずり出して乾かしていた、というエピソードもあります。
そんな、生きられるか分からない時代の中でピアノと共に生きたダン・タイ・ソン。彼がピアノで奏でる音楽はまさに「命」そのものでしょう。その中でもショパンの音楽にとりわけ大きな愛着とこだわりを持ち続ける、 文字通り「ショパン弾き」のダン・タイ・ソンの演奏、一度は生で聴きたい人物の1人です。
ブルース・リュ
ブルース・リーに似ていると言われていたため、自分で「ブルース」という名前を付けました!外見だけでなく、演奏も「息をのむような美しさ」!
一瞬「ブルース・リー」と読み間違えそうな名前のピアニスト、その名もブルース・リュ!ブルース・リーに似ていると言われていたことや、ブルース・リーが好きだったため、2020年頃に「ブルース」をファーストネームに加えました。
つまり「ブルース」は芸名で、本名は「シャオユー・リウ」中国系カナダ人のピアニストです。
見た目も美しいですが、彼も音楽もまた特筆すべき美しい音色と完璧なテクニックで世界中の聴衆を魅了し続けています。
彼の演奏は「息をのむような美しさ」と評価されています。
その実力はコンクールでもお墨付きで、2021年の第18回ショパン国際ピアノコンクールで優勝し、カナダ人として初めてこの栄誉に輝きました。
コロナ禍という、今までと違ったコンクールの状況の中で優勝したこともあり、一際注目を浴びました。
優勝するほどの音楽的才能を持つブルース・リュですが、ショパン国際ピアノコンクールの予選後に「ダメなら帰ろう」と思って荷物をまとめていたという面白いエピソードもあります。
現在も活躍中のピアニストで、世界中でコンサートやリサイタルを行っています。
実は先ほど紹介したダン・タイ・ソンの弟子で、現在も師弟関係を続けています。ブルース・リュのモットーは、常に新しいアイディアを演奏に盛り込み、新鮮さを備えたみずみずしい演奏をすることです。
この演奏スタイルは、常に観客を虜にして飽きさせず、彼の演奏に常に期待感を持たせてしまうのも納得でしょう。
アレクサンダー・コブリン
コンクールでその時の優勝者を持ち上げて賛辞を送った、素敵なピアニスト!
アレクサンダー・コブリンは、ロシアのピアニストです。
1998年にグラスゴー国際ピアノコンクールで優勝し、1999年にはブゾーニ国際ピアノコンクールでも優勝しました。
2000年にはショパン国際ピアノコンクールで第3位に入賞しました。
そのショパン国際ピアノコンクールで第3位の時は多くの人の記憶に焼き付けたシーンがあります。
その時の優勝は「ユンディ・リ」というピアニストでした。優勝が決まった瞬間に、コブリンがユンディを即座に持ち上げたのです!彼の音楽に対する深い愛と、人柄を表したエピソード!
コブリンは近年、ベートーヴェンのピアノソナタ全曲録音に取り組んでいます。
ベートヴェンのピアノソナタは全部で32曲あり、全て演奏しようと思うと約11時間半かかります。
そんな素敵な人間性と、挑戦をし続ける情熱的な人間が描く音楽はどんな物なのか!ぜひ生で聞いてみたい一人です。
反田恭平
半世紀ぶりに日本の名を世界に!実業家でもあるピアノ界の異端児!
日本でその名を知らない人はいないであろう反田恭平。
また「ショパンコンクール」と言う名前をクラシックを全く知らない人でも連日のニュースで覚えた人も多いのではないでしょうか。
彼がなぜこれだけ取り上げられたかというと、先ほど挙げた「ショパンコンクール」に関係しています!
そもそもショパンコンクールで邦人が入賞したのが半世紀ぶりで、(正確には51年ぶり!)しかも最高位タイなので、メディアも黙っていられるわけがないですよね!
例えば、国際的なテニスの大会で日本人が2位になったと言うくらい驚きの結果と同じものです。
ショパンコンクールで一躍有名になったわけですが、その以前も様々なコンクールで華々しい成績を残しています。
2009年に第2回エレーナ・リヒテル国際ピアノコンクール1位に入賞。2012年に「第81回日本音楽コンクール」で第1位と聴衆賞を獲得など、ショパンコンクール前からそのポテンシャルの素晴らしさは轟かせていました。
ショパンコンクールで注目を集めるようになった反田さんは、その後も引き続き各地でのコンサートをはじめ、なんと自身が創設したジャパン・ナショナル・オーケストラのプロデュースや指揮を行っています。
またクラシック音楽の普及に尽力しており、レーベル「NOVA Record」を立ち上げています。
もはや反田恭平という人間の才能は、演奏だけでは収まらず指揮、実業家にまでその才能を余すことなく発揮しているのですね。
そんな様々な挑戦を積み重ねている彼は「美しい音色と繊細な表現力を持つ、音楽の本質を引き出すピアニスト」です。高音は天国のような音を出し、低音は体内に響く重厚な音を出すことが特徴です。今後さらにその人生経験から紡ぎ出される音楽の成長に期待をせざるを得ません。
きっと生で何回聴いても、毎回違う反田恭平の世界に引き込まれることでしょう!
マルタ・アルゲリッチ
ぜひ別府で温泉と音楽を楽しんでね!「ダイナミックで華麗な情熱的」で時代が進むごとに変化が楽しめる世界的女性ピアニスト!
アルゼンチンに生まれた世界的に有名なピアニスト、マルタ・アルゲリッチ。
神童として注目され、5歳でピアノを始めました。8歳でモーツァルトとベートーヴェンのピアノ協奏曲を演奏し、デビューしました。
その瞬間、彼女のピアノの才能は見出され、現在に至ると言うのですから人生どんなことがきっかけで何が起こるか分からないものです。
コンクールでもその才能は光らせ、1957年にブゾーニおよびジュネーヴの国際コンクールで優勝し、1965年にショパン国際ピアノコンクールでも優勝しています。
またコンクールの賞だけでなく、テレビで聞いたことがあるであろうグラミー賞やショック賞、グラモフォン誌のアーティスト・オブ・ザ・イヤー賞なども受賞しているグラミー賞やショック賞、グラモフォン誌のアーティスト・オブ・ザ・イヤー賞など、まさにピアノ界の女神のような存在です。
アルゲリッチの演奏は、特に「男性的」と評される力強さと、アルゼンチン出身にふさわしい情熱を持ちます。
ダイナミックでエネルギッシュな表現力が特徴です。
しかし、演奏とは真逆のこんなエピソードがあります。
そんな中、コンサートを行うのですから彼女のエネルギーは音楽に集まり、人が変わったように情熱とエネルギーに溢れるのも納得です。
アルゲリッチは大分県別府市との関係が深く、1994年から別府ビーコンプラザ・フィルハーモニアホールの名誉音楽監督を務め、1998年からは「別府アルゲリッチ音楽祭」の総監督を務めています。
2021年には、彼女の誕生日である6月5日が「マルタ・アルゲリッチの日」と制定されました。アルゲリッチの人柄を知った上で、別府の温泉と音楽両方楽しむ旅行なんていうのも乙な物です。
アンドレイ・ガブリーロフ
個性爆発!お騒がせ奇才ピアニストで、世界を魅了し続ける!
アンドレイ・ガブリーロフは、ロシアのピアニストで、彼は常に個性を全面に出した演奏によって人々を魅了しています。
ピアノとの出会いは3歳で母親から手ほどきを受けました。
母親もピアニストでしたので、幼少期からピアノに触れるのは必然だったのかも知れません。そしてその才能を余す事なく伸ばし、コンクールでも素晴らしい成績を残し、1974年、18歳でチャイコフスキー国際ピアノコンクールで優勝し、歴代最年少の記録を樹立したのです。
1990年代後半から2000年初頭にかけて、演奏活動から遠ざかり、哲学や宗教の研究に没頭ていたのです。
演奏家としてのキャリアが順調だったにもかかわらず、自分自身に満足していなかったと述べています。
彼は「普通の人間」としての人生経験が不足していると感じ、演奏活動から離れて宗教や哲学を研究することで、人生の新たな意味を見出そうとしたのです。
そのためには新しい音楽のアプローチ法を模索する必要があると考えました。
その後、その深い精神的な音楽への理解を学んだガブリーロフは、新しいピアニスト「アンドレイ・ガブリーロフ」として今もコンサートで人々に音楽を伝え続けています。
特に有名なものは、彼が突然演奏会をキャンセルしたり、ステージ上で演奏を中断することがあったことです。またベルギーでのコンサートやウィーンでのラジオ生放送中に演奏を中断したことが話題になりました。
これらの行動は、ガブリーロフの個性とともに、彼の演奏家としてのキャリアに影響を与えました。
そんなガブリーロフの演奏、実際に聴いたらどんな世界に引き込まれるのだろうと、考えるだけでワクワクしてきます。
アレクセイ・リビュモフ
「ロシアの最後の巨匠」と呼ばれるピアニスト!一度引退宣言したけど、広島でリサイタルを開催!
アレクセイ・リュビモフは、1944年モスクワで生まれたロシアのピアニストでありながら、チェンバロの奏者でもあります。
リュビモフはコンクールの経歴よりも音楽活動、特に現代音楽の紹介や古楽器(チェンバロ)演奏において重要な役割を果たしており、コンクールでの成績以上高く評価されています。
その評価は「ロシアの最後の巨匠」と言われるもので、決して目にみえる成績では表すことのできない彼への信頼が伝わってきます。
実はリュビモフ、2019年にコンサートホールで引退を宣言し、来年の7月でオーケストラとの共演を終わらせると発表しました。
「自分の納得できる演奏ができるうちに引退したい」という思いからだったようです。
しかし2020年以降、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、リュビモフは再び演奏活動を再開しました。
彼は「自分が今できることは演奏すること」と決め、特に広島での演奏を希望し、2023年4月14日に広島で開催したコンサートを開催ました。
他にも、彼の信念を垣間見るエピソードが。。
2022年4月にモスクワで開催されたコンサートで、警察が「爆破予告がある」という口実で公演を中止させようとした際、リュビモフはシューベルトの即興曲を最後まで弾き続けたと報告されています。
この行動は、リュビモフの音楽への情熱と、政治的圧力に屈しない姿勢を示すものとして注目されています。
そんな、祈りの音楽を捧げ続けるロシアの巨匠。一度は生で聴いて、彼の心情に触れてみたいです。
内田光子
日本人初!ショパン国際ピアノコンクールで第2位の快挙!でありながらモーツァルトの名手なんです!
先ほどの反田恭平さんの時「ショパンコンクールで邦人が入賞したのがなんと半世紀ぶり!」という紹介をしたの覚えていますでしょうか!?
実は今からご紹介するピアニスト、内田光子さんが初代ショパン国際ピアノコンクールで第2位を獲った方です。
日本人女性として初めてオリンピックのフィギュアスケート競技で金メダルを取る快挙を成し遂げた荒川静香さんと同じです。
さて、そんな経歴を聞くと「じゃあ内田光子はショパンコンクールで有名になったんだ!」と思う方もいるかも知れませんが、
実は、内田光子さんは、モーツァルトのピアノソナタとピアノ協奏曲の全曲演奏会およびその録音全集で世界的に有名になりました。
「内田さんは、モーツァルトが一番好きなんだ。」と思われるかも知れませんが、”魔王”や”野ばら”でお馴染みの作曲家であるシューベルトを非常に愛し、作品を研究されています。
内田さんはこれまでに、『死ぬ時にはシューベルトを弾いていたい』と語るほどシューベルトへの愛が強いピアニストです。
現在は海外籍で主に海外での活動が中心ですが、クリアな音が特徴で、知性・感情のバランスが整っている内田さんの演奏で、ダイナミクスさのあるシューベルトの魔王を聴いてみたいです。
生で聴いてみたかった!ピアニスト3選
ホールに響く一音一音で会場全体を虜にしてしまう、そんな”奇跡”としか言えようのない、生の演奏を体験できた方は本当に幸運でした。
しかし、彼らが残した録音や記録からは、当時の聴衆を圧倒した圧巻の技巧や深い表現力を、今でもはっきりと感じ取ることができます。
なぜ彼らが巨匠・名人などと呼ばれるのか?またエピソードからなんと呼ばれていたのかなど、人としての魅力も語る上で外せない!
今回は、”一度だけでも生で聴いてみたかった”と多くの方に惜しまれつつも、その足跡と芸術性が今なお色褪せない、歴史的に有名な世界的ピアニストをご紹介します。
マウリツィオ・ポリーニ
「ミスター・パーフェクト」とは私のことです!その名に恥じぬ、正確な演奏でエピソードで聴衆を魅了!
マウリツィオ・ポリーニはイタリアのミラノ生まれのピアニスト。2024年3月23日に同地で逝去しました。
彼の演奏は何といっても完璧なテクニックと透明感のある音色が特徴です。
その演奏から「ミスター・パーフェクト」という名で知られ、いかに音楽の正確さを追求してきたかが分かります。
こういったことからも、音楽へのこだわりが幼少期から培われたのは言うまでもないでしょう。
その音楽への追求心と技術力は実際にコンクールでも、目に現れる形で残しています。
ジュネーブ国際ピアノコンクールでは1957年に15歳で第2位を獲得し、1958年にも再び第2位となりました。
また1960年に18歳で第6回ショパン国際ピアノコンクールに審査員全員一致で優勝しました。
ただ完璧に正確に演奏するのではなく、作曲家への尊敬の念と内に秘める思いをピアノで表現していることも、この結果から伝わります。
東京文化会館でのコンサートのことです。リハーサルの時からピアノの調整に非常に時間をかけ、彼はスタッフにピアノを弾いてもらうよう指示し、フォルテとピアニシモの音色を確認しながら、ピアノの位置を微妙に調整していました。
この準備には非常に時間がかかり、スタッフは非常に苦労したという話です。
ポリーニとしては、完璧を目指していたので準備に時間をたくさんかけるというのは至極当然だったのかも知れません。
もしも、また聴けるのであれば、リハーサルの時からその様子をチケットを買ってでも見てみたいと思ってしまいます。
ウラディミール・ホロヴィッツ
「ライヴの人」と呼ばれてました!SNS発信はきっとやらないだろう、その舞台上でしか得られない特別なエネルギーや感動に涙する!
ロシア帝国(現ウクライナ)生まれで、子供の時のあの素直さと、大人の艶やかな感性をこれでもかと音楽に注ぎ込んだホロヴィッツ。
彼の異名「ライブの人」というのは、性格からきています!現代では心理学や、生きやすい世の中になるように「個性」というのが日本でも受け入れられるようになってきました。
ホロヴィッツはまさに「生きやすさ」と戦っていたのかも知れないというエピソードがあります。
ホロヴィッツは非常に気難しい性格で知られています。
インタビューの際、機嫌が悪い日には質問を避けたり、時間を厳守するなど、プロ意識の高さとともに、気難しさも伝えられ、非常に個性が強く、神経質な性格というわけですね。
しかし、それを凌駕するホロヴィッツの演奏!先ほどの「ライブの人」という名の通り、舞台上での演奏が彼の真の姿を表すとされています。
彼の演奏は、聴衆の前でだけが本来の力を発揮するとされ、同じ曲でも二度と同じように弾かれることはないとされています。
なのでSNSの発達した現代でも、ホロヴィッツは発信をしたのだろうか?と思ってしますほど、生の演奏の魅力に惹き込まれるのですね。
ホロヴィッツは健康上の理由や精神的な不安定さからしばしば公の活動から遠ざかっていましたが、舞台に戻るたびに「ヒストリック・リターン」として大きな注目を集め、再び彼の演奏の力が世に知らされました。
生の演奏会でも、ドラマが生み出されています。今ももし聴けたら、そのような人間性の部分含めて殺伐とした世界に「色」を与えてくれるのでしょう。
スヴャトスラフ・リヒテル
「音楽のドン・ファン」と称されてました!そんな彼の愛用のピアノは日本が誇るYAMAHAピアノ!
ウクライナ生まれのスヴャトスラフ・リヒテル。
「第九」や「運命」で有名なベートーヴェンや音楽の授業で習った「野ばら」や「魔王」を作曲したシューベルトの作品を得意としていました。
彼はとにかく手が大きくて、卓越した演奏技術で人々を魅了していました。
リヒテルは「音楽のドン・ファン」と称されていたのですが、「ドン・ファン」はスペインの伝説上の人物で、理想の女性を追い求め、自由気ままに生きる人物として知られています。
音楽に対する姿勢や演奏スタイルが「ドン・ファン」のような自由奔放で理想を追求する精神に似ているため、「音楽のドン・ファン」と称されることになりました。
そんなリヒテルですが、ずっと愛用していたピアノがあります。
それは日本が誇るYAMAHAのピアノなのです!
ではYAMAHAと出会ったのは日本なの!?と一瞬思ってしまうかも知れませんが、残念ながら日本ではありません。
イタリアのパドヴァでヤマハのピアノと出会い、それ以来ヤマハを愛用しました。来日公演やヨーロッパツアーでも可能な限りヤマハを指定してしたほどです。
音楽のドン・ファンが日本のYAMAHAピアノで奏でる音楽は非常に興味深い物です。生での聞き応えは言わずもがな、といったところですね。
そしてこれから世界的ピアニストになるとされている日本のピアニスト
藤田真央
コンクールで、スタンディングオベーションを受けました!情熱大陸にも出演して、その練習風景にファンの心を鷲掴み!
今や日本が誇る新星ピアノストといえば、藤田真央でしょう。
彼を語る上で2019年のチャイコフスキー国際コンクールの話は外せません!
そのコンクールでは第2位という本当にすごい結果を残しておりますが、結果を凌駕する印象的なエピソードがあります。
また人間性も非常に親しみやすく、彼の素晴らしい音楽性と人間性によりファンが増え続けているというのも「カリスマ性」を備えた人間のなせる技かも知れません。
彼がメディアに出たもので非常に印象的だったのは情熱大陸で練習の様子が映っていた時のことです。
自宅でスメタナの「ピアノ三重奏曲」を練習する様子が映し出されました。彼はピアノ以外のパートを口ずさみながら練習に没入し、瑞々しく多彩な音色と、繊細かつ圧倒的な表現力が印象的でした。
今をときめく藤田真央さん。ソニークラシカルと専属レコーディングのワールドワイド契約を締結しました。
これは日本人ピアニストとして初めての快挙!アルバムはデビュー・アルバムとして全世界にリリースされ、注目を集めています。今後の活躍に目が離せません!
務川慧悟
反田恭平さんとの出会いが人生を変えた!ラヴェルと一緒にピアノの人生を歩んでいるかのような、深い愛情を感じます!
パリ国立高等音楽院に審査員満場一致の首席で合格したという、今の一言だけでも強烈な印象を持たせる務川慧悟さん!
その実力は世界が認めるもので、実際に2021年にエリザベート王妃国際音楽コンクールで第3位、2019年にロン=ティボー=クレスパン国際コンクールで第2位を獲得し、国際的な注目を集めています。
そんな務川慧悟さんが最も注目されるきっかけとなったのが、ラヴェルの「ピアノ協奏曲ト長調」を初演奏した時です。
ラヴェルは「ボレロ」などで日本でもテレビなどで使われているお馴染みの作曲家です。
さて、話は戻りこの演奏はファンから大きな期待を集め、会場を感動で満たしました。彼はこの曲を「この世で最も愛してやまない」と語っています。実ははパリに留学する前はラヴェルよりもドビュッシーの音楽を好んでいましたが、パリでラヴェルに深く惹かれるようになりました。
実は務川慧悟さんは、反田恭平さんとの出会いが人生を変えたと語っています。反田さんは務川の事務所の社長であり、相方でもあります。今後2人が更にクラシック音楽界に、新しい風を吹かせると思うとワクワクが止まりません。
西本裕矢(現役東京藝大生)
東京芸術大学に在籍しながらその実力はすでに世界が注目中!クラシック音楽界の超新星!
西本裕矢さんは現在学生でピアノを学んでおられながら、すでにその才能は世界から注目されています。
実際にコンクールでもアメリカ・ワシントンDCで開催された第68回コシチュシュコ財団ショパンピアノコンクールで第1位及び「シマノフスキ最優秀演奏賞」を受賞しました!
そのコンクールで素晴らしい成績を収めたわけですが、彼は本当にショパンを愛しているということが、様々な視点から汲み取れます。
例えばオール・ショパン・プログラムを演奏することも多く、ショパンの「マズルカ」や「ノクターン」、「ポロネーズ」などの作品を優雅に演奏したり、「エチュード」や「バラード」、「英雄ポロネーズ」も得意としており、ショパンの即興性にマッチした自由で明るい音楽性を発揮しています。
日本人にとって、ショパンは一番聞き馴染みがあり癒される方も多いでしょう。
ショパンを得意とする超新星の演奏は私たちを新しいショパンの一面を見せてくれるかも知れません。
面白エピソードを見て、その人の人間性に興味を持って聞いてみる!という聴き方も一つの正解です!
名前を知っている、テレビで見たことある、など色々なきっかけがあると思います。どれも正解です。音楽に正解はないですし、現状の自分に合った音楽を楽しむことが一番です。今回述べた方達は一人一人が本当に素晴らしいピアニストたちです。そこから派生して面白エピソードを追加しました。音楽だけでなく「人」の部分を見て興味を持っていただけたら嬉しいです