多くのアーティストが様々な楽曲をSNSやCD・アルバムにアップロードし、街中や電車で日々耳にするメロディーもあると思います。
大人になると、ライブにもいく機会も増え、好きな曲に出会うと「自分で演奏できたらいいな。」
ライブやコンサート、テレビ番組などでピアノの演奏を見たときに、「演奏している人が輝いて見えた。」
そうした体験があると”自分も弾いてみたい、演奏したい!”と思う曲もあるはずです。
テレビやMVで華やかにピアノを弾いているように見かけるかと思いますが、実際は地道な練習があってはじめて”演奏”が成り立っています。
本記事では、趣味としてピアノをはじめてみようかな?と検討している方に、大人の趣味としてピアノの魅力についてご紹介していきます。
- 1 ピアノを大人の趣味として楽しむメリット・ピアノがもたらす効果
- 2 ピアノを趣味として続けて上手になるための練習方法
- 3 ピアノを趣味として始めた方の基礎練習としておすすめの教材
- 3.1 ピアノを趣味として始めた方におすすめの教材:基礎力を養えるバイエル
- 3.2 シャルル=ルイ・ハノン(Charles-Louis Hanon)は、19世紀のフランスの作曲家であり、ピアノの教育者でした。彼が作った『ピアノ練習曲集』は、ピアノのテクニックを強化するための練習曲が含まれており、特に指の独立性や筋力の強さを養うための練習が重視されています。この練習曲集は、初心者から上級者まで幅広いレベルのピアニストに使われています。
- 3.3 ピアノを趣味として始めた方におすすめの教材:指の独立性を養えるハノン
- 3.4 ピアノを趣味として始めた方におすすめの教材:テクニック&表現力を段階的に伸ばすチェルニー
- 4 まとめ
ピアノを大人の趣味として楽しむメリット・ピアノがもたらす効果
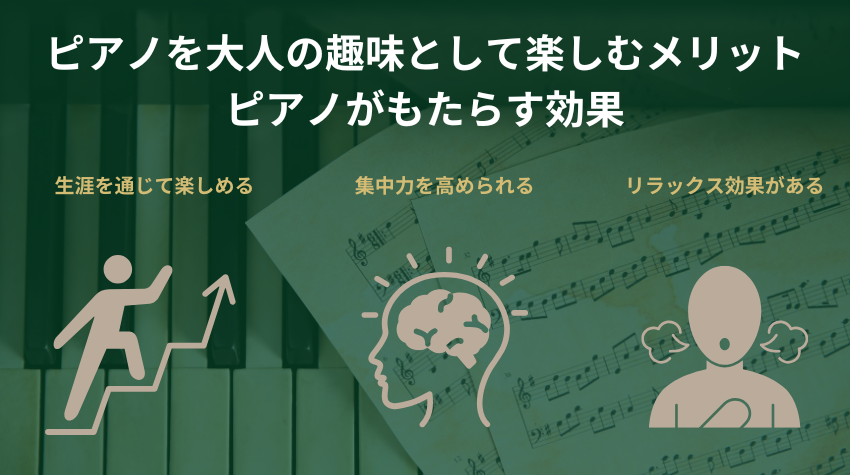
趣味があることで、仕事と休日の切り替えがしやすくなることや、健康的で充実した日々を過ごしやすくなりますよね。
大人になると、習い事をする機会も減り自分で見つけないとなかなか見つからない。というお話もよく聞きます。
そうした、趣味を持つ機会がなかった方は、好きなこと、趣味の見つけ方がわからないというお話も聞きます。
生涯を通じて楽しめ、技術を磨くことができる
ピアノは座った姿勢で演奏するため、激しい運動を伴うスポーツと異なり、体力的な負担が比較的少ないです。
さらに、昔に比べ電子ピアノの普及によって騒音やスペースの問題を解消しやすくなり、自宅やスタジオなどで練習を続けられる環境が整いやすくなりました。
さらに、クラシック、ポップ、ジャズなど、多くのジャンルので鍵盤を通じて様々な曲に触れ続けることができるため、マンネリを感じることなく、新しい目標を立てやすいです。
一つづつ目標を達成して過程で、「もう少し音の粒を揃えてパラパラと弾きたい。」といった気持ちや「今よりも少し速く弾けるようになりたい」「もっと繊細な表現で演奏したい」のような具体的な技術向上のモチベーションが湧いてきます。
ピアノで得られる達成感とそれに伴う成長は、昨日と同じはずの日常が新鮮に映るようになり、”できることが増えていく”ことで、これまで見えて来なかった可能性や楽しみを見出しやすくなります。
さらに、「もっと挑戦したい!」という興味・関心の幅が広がります。
集中力を高められたり、リラックス効果も得られる
ピアノ演奏では、両手の指づかい、楽譜の読み取り、ペダル操作、リズム強弱のコントロールを同時に行うため、多くの脳機能を並行して使います。
そうした多くの機能を使いながら、目の前の演奏に集中しなければ演奏することはできません。
イギリスの国立大学であるバース大学による研究によると、ピアノの練習は心の健康に大きな影響を与えることが明らかになったと発表しています。
演奏に集中する、没入状態によって他のことを考えることなく演奏に集中して取り組めるのでリラックスした状態に近づけるとされています。
ピアノを弾くことは、自己表現の一つでもありますし、一定のリズム・メロディを繰り返し演奏すると心拍・呼吸が安定するという事例もあり、音楽療法として用いられるケースもありますよ。
ピアノを趣味として続けて上手になるための練習方法
仕事や家事、育児など日々の優先事項がある中で、ピアノに費やす時間は限られがちですよね。
趣味といっても好きだからこそ、「もっと上手く弾きたい」という気持ちや理想が高まってしまい、練習できないと焦りを感じることもあるはずです。
「今日は忙しくてピアノを弾けなかった。」
「前は曲が弾けたはずなのに、久しぶりにピアノを弾いたら忘れてしまった…」
など、誰しも経験することです。
練習しない日が続いたり、思うように進まない時期は、自己嫌悪に陥りやすいかもしれませんが、そういった気持ちが湧くのは”ピアノに対して真剣に取り組んでいる”証拠でもあります。
焦る気持ちはあるかもしれませんが、「半年後、1年後、5年後」といった長いスパンで少しずつでも進歩していけばいいなという、気持ちを大切にすると心が楽になります。
ここからは、長時間の練習が取れない方におすすめの短い時間でも続けやすい気持ちにするためのコツをご紹介します。
時間を決めて練習内容を限定する
ピアノを練習するといっても、基礎練習、全体練習や部分練習などさまざまな練習があります。
日々全ての練習をこなすのは困難であり、基礎練習だけでも続けられると反復学習をしやすくなります。
基礎練習を繰り返すと、右手・左手それぞれの指が満遍なく動かせるように作られているのですが、毎日続けることが大変だと思われている方に練習の向き合い方からご紹介します。
朝の支度前の5分、夕食後の10分など自分が無理なく確保しやすいタイミングを決めて鍵盤に触れる習慣を作ると毎日鍵盤に触れ続けやすいです。
例えば、「冒頭の8小節だけを弾きこむ。」など、少しずつ確実に指が動くなるようになると、それがモチベーションとなり、練習を続けやすくなるます。
完璧を求めない練習を意識する
仕事・家庭の用事をこなしながらのピアノでは、「ミスを減らしたい」「上手く弾けるようになりたい」という気持ちがあっても、あまり完璧さを追い求めすぎると続けることがしんどくなってしまいます。
ミスすると自己嫌悪にもなるし、人前で弾くことが怖くなることもありますよね。
「練習曲をとりあえず、最後まで弾けたら合格」
「自分の中で納得のいくフレーズが一つでも増えたらOK」
といったように、練習目標を小さく設定しておくことでピアノを楽しみながら続けやすいです。
限られた時間を有効に使うために、短い時間でも自分の演奏を録音して聴くと、「意外と指が転んでいる」といった気づきを得られます。
録音を聴き直すことで、自分の演奏を客観的に振り返ることができるのでどの部分を重点的に練習するべきか。といった発見を早い段階で得ることができます。
ピアノを趣味として始めた方の基礎練習としておすすめの教材
ピアノを始めたばかりの方にとって、基礎練習と聞くと「ただ指を動かすだけの単調な練習」だと思われるかもしれません。
ですが、基礎練習を繰り返すことで指の動きを均等にし、指の筋力アップに伴う独立性アップが期待できます。
ピアノを趣味として始めた方におすすめの教材:基礎力を養えるバイエル
バイエルは(Friedrich August Bayer)は、19世紀のドイツの作家でピアノの先生でした。
バイエルの【バイエル教則本】は、ピアノ初心者が導入から基礎を体系的に学べる王道の教本で譜読み、リズム、指使いなどピアノ演奏に必要な要素が総合的に学べるように作られています。
難易度が緩やかに上が理、簡単な曲から曲を段階的に学べるように作られているので、技術を習得しやすい内容で、左右の譜読みや拍子感など演奏に必要な基礎力を身につけやすいことも特徴です。
バイエルをしっかりとこなしていくことで、その後の簡単な曲やポピュラー曲にも応用が効かせやすくなります。
シャルル=ルイ・ハノン(Charles-Louis Hanon)は、19世紀のフランスの作曲家であり、ピアノの教育者でした。彼が作った『ピアノ練習曲集』は、ピアノのテクニックを強化するための練習曲が含まれており、特に指の独立性や筋力の強さを養うための練習が重視されています。この練習曲集は、初心者から上級者まで幅広いレベルのピアニストに使われています。
『ピアノ練習曲集』は全60曲から成り、これらの練習は基本的な指使いや手の動きの練習を目的としています。例えば、ハノンの有名な「指の独立性を高める練習」や「音階の練習」は、ピアノを弾く上でとても大事なテクニックを養うことができます。これらは、指の筋力を強くすることが出来ます。
ピアノを趣味として始めた方におすすめの教材:指の独立性を養えるハノン
シャルイ=ルイ・ハノン(Charles-Louis Hanon)は、単調な反復パターンの中で指を均等に動かす練習ができます。
ピアノを始めたての方にとって、よくある悩みとして、指ごとの力の偏りが生じやすいことがありますよね。
ハノンでは、恩恵がパターン化されているので譜読みの負担が少ない分、指・手首の動きに集中でき集中力・持久力も身につきます。
指の独立性や筋力アップは、ピアノの演奏において欠かせないもので、右手の中指と薬指が同時に動かないようにすることや左手の小指でベースを弾きながらも、薬指・中指で和音をしっかりと支えることなど役割を分担して正確に動かすために欠かせません。
さらに、ピアノの鍵盤は鍵盤を指先でしっかりと押さえ込む力が必要で、力が足りないと音が弱くなったりバランスが崩れてしまいます。
指先に適度な筋力をつけることで、思ったとおりの強さ・速さで鍵盤を押せるようになり、速いパッセージを弾く時も指が疲れにくく安定した演奏ができるようになります。
ピアノを趣味として始めた方におすすめの教材:テクニック&表現力を段階的に伸ばすチェルニー
チェルニー(Czerny)は、19世紀のオーストリアの作曲家で、ピアノ教育における教材作曲家として広く知られています。
チェルニー練習曲の特徴として、ハノン、バイエルと異なりメロディ性やリズムのバリュエーションがあり、練習しながら音楽的表現を学べます。
単調ではないものの、演奏すことに飽きがきにくく”曲を弾く”感覚で練習できることが特徴です。
チェルニーも段階的に難易度が上がるため初級から上級まで対応しやすく、「音楽として弾く楽しさ」を感じやすいので実際の曲にも応用しやすいです。
チェルニーのエチュードは、”練習曲”でありながらも、本番の曲にも出てくるようなスケールや和音、アルペジオのパターンが盛り込まれているので、クラシックの有名曲やポップスなどさまざまな曲を弾く準備としてもおすすめです。
まとめ
ピアノは金管楽器・木管楽器と異なり、鳴らすと音が出る楽器ですが、音の強弱、タッチのコントロール、リズム・テンポの揺らぎなど、知れば知るほど奥深い楽器です。
鍵盤を押すことで音は出ますが、指先だけで激しく押し込む場合と指元から全体的に押し込む場合では音の波長の長さ、大きな音の伝わり方が変わってきます。
技術が身につくと、意図的に自分が演奏したい曲に合わせて微妙な”間”や”流れ”を自在に操れるようになりますので、趣味として楽しみながら技術を身につけていきましょう。
